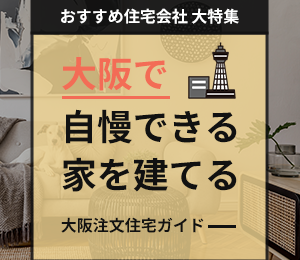大阪で注文住宅を建てる際は耐震等級が大切!種類と基準
公開:2023.12.08 更新:2023.12.08
耐震等級は、2000年に施行された法律に基づき、建物の地震への耐力を示す指標です。この等級は1から3まで存在し、各等級は性能向上を段階的に表現しています。等級1は最低限の耐震機能を備え、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性能を有しています。
これにより、地震の多い国での住まい選びにおいては、耐震等級の理解が重要です。等級が高いほど耐震性が向上し、安全で信頼性の高い住まいを選ぶ際の指標となります。
目次
耐震等級とは?耐震等級の種類
「耐震等級」とは、2000年に実施された地震に対する建物の耐力を示す指標です。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」に基づいて設けられた規定で、耐震等級1から等級3までが存在し、各等級は性能の向上を段階的に表現しています。
耐震等級1は、建築基準法に従い「最低限の耐震機能を備えた建物」を指し、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性能を有しています。地震の頻発する国での住居選びにおいて、耐震等級の理解は重要です。これに基づき、安全かつ信頼性の高い住まいを選びましょう。
耐震等級の種類
耐震等級には、等級1、等級2、等級3の3つのカテゴリが存在します。これらの数字は建物の耐震性を示しており、等級が向上するほど、その家が高い耐震性を持つと評価されます。
耐震等級1
耐震等級1は、建築基準法に基づいた耐震強度を備えています。この等級は、100年に1度の強い地震(震度6強〜7)に対しても倒壊・崩壊しないように設計されていますが、一定の損傷が生じる可能性を考慮するべきです。
1981年6月1日以降に建てられた全ての建物が耐震等級1以上の基準を満たし、「建物における最低限の耐震性能を備えている」ことを示しています。この等級は、数十年に1度の地震(震度5)に対しては損傷しない程度の性能を有しているとされています。
耐震等級2
「長期優良住宅」の認定基準に組み込まれた耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震強度を有しています。この等級は、100年に一度の地震(震度6強〜7)に耐え、軽度の補修を施せばその後も長期間にわたり住み続けることができる基準で設計されています。
災害時の避難先として指定される学校や病院などは、耐震等級2以上の性能が確保されています。
耐震等級3
耐震等級の最高水準である等級3は、150年に一度起こるような大きな地震でも倒壊や崩壊の危険がないほどの高い耐震性で設計されています。
災害発生時に救護支援や復興拠点となる警察署や消防署などは、その多くが耐震等級3で設計されています。耐震等級3は等級1の1.5倍の耐震強度を有し、震度6強〜7の地震にも抵抗できる能力があります。
耐震等級の基準とは?
建物の重さ
建物が軽いほど、その耐震性は向上します。建物が重い場合、地震時の揺れが大きく、それに伴って建物へのダメージも増加します。対照的に、建物が軽ければ地震の揺れが小さくなり、その結果、建物への影響も軽減されます。
例えば、鉄骨造やコンクリート造は重量がありますが、木造はこれらと比べて軽量であるため、一般的には地震に強いとされています。
耐力壁の数
耐力壁は、地震や風などの横からの力に対抗するための壁であり、これらの壁が増えれば増えるほど、建物の耐震性が向上します。したがって、耐震性を向上させるためには、耐力壁の数を増やすことが重要です。
ただし、無計画に耐力壁を配置するのではなく、配置のバランスを考慮することが重要です。例えば、1階と2階の耐力壁を揃えたり、四隅を支えるようにバランス良く配置したりすることで、効果的な耐震性向上が期待できます。
なお、耐力壁を単に増やすのではなく、均衡の取れた配置が大切です。特定の箇所にだけ耐力壁が集中するような、均整の取れていない構造は、逆に耐震性が低下することがあります。
同様に、耐震金物などで耐震性を向上させる際も、全体のバランスを考慮して、均衡のとれた配置を心がけましょう。
床の耐震性
壁だけでなく、床の耐震性も重要です。なぜなら、壁と床は連携しているからです。壁が頑丈でも、土台である床が損傷や崩壊すれば、地震の揺れに十分に耐えられません。床に優れた耐震性能があれば、耐力壁が受けた揺れを吸収し、ダメージを最小限に抑えることができます。耐震等級2・3では、床の剛性(水平構面)も計算され、床の耐震性も確保されています。
耐震等級を知るにはどこを見ればよい?
耐震等級の評価基準は、2000年に施行された「住宅性能表示制度」に基づいています。住宅性能表示は、建物の品質を専門家が一定の基準で評価する制度であり、任意の制度であるため、全ての住宅が評価を受ける必要はありません。
通常、耐震等級を知るためには「住宅性能評価書」(住宅性能評価の結果をまとめた書面)を確認することが一般的ですが、これを取得していない場合もあります。その際、専門機関に依頼して「耐震診断」を行うことで、住宅の耐震性などを診断できます。
新築を検討する場合は、耐震等級を知りたい時点で施工を依頼する業者に相談し、住宅性能評価書の交付に必要な書類(設計図面など)を提供することが重要です。住宅性能評価書の取得には手続きが必要ですが、これにより住宅ローンの引き下げや地震保険の割引など、様々なメリットが享受できます。
耐震等級は、建物の地震への耐力を示す指標で、耐震等級1から3まで存在します。これは住宅品質確保法に基づくもので、各等級は性能向上を段階的に表現しています。
耐震等級1は最低限の耐震機能を有し、等級2は1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性能を持っています。重要なのは、地震の多い国で住まいを選ぶ際に耐震等級を理解することで、安全で信頼性の高い住宅を選ぶことができます。
建物の重さも耐震性に影響を与え、軽い建物ほど揺れに強くなります。木造が地震に強いとされるのはそのためです。耐力壁も耐震性向上の要素であり、配置のバランスが重要です。無計画に配置するのではなく、バランスよく配置することで効果的な耐震性向上が期待できます。床の耐震性も注目すべきで、耐震等級2・3では床の剛性も計算されています。